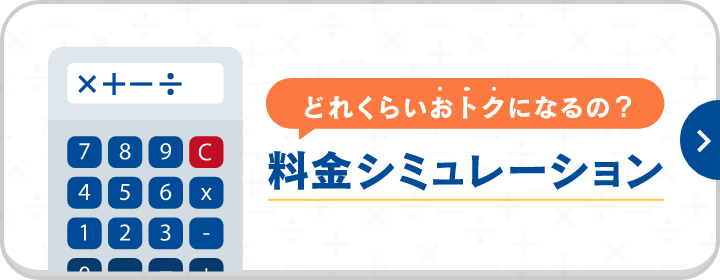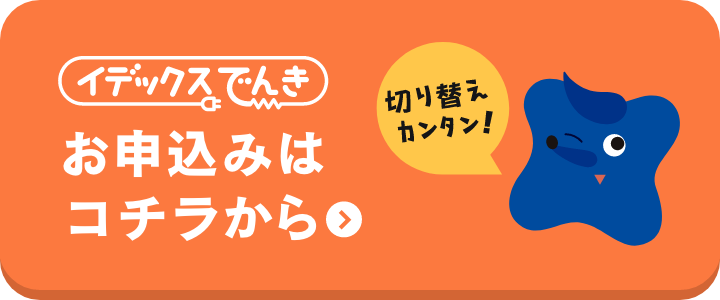アンペアとは?電気代との関係や節約するコツを紹介
2025.05.02
- ライフスタイル
- 節約
- 光熱費
- 節約
- 電気代
- 電気契約
アンペアとは、電気が流れる電気量を指し、電気代の節約には契約アンペア数の見直しが効果的です。本記事では、基本料金の仕組みや確認方法、無理なく見直すためのポイントをわかりやすく紹介します。節電を検討中の方は、ぜひご一読ください。
毎月の電気代が高いと感じたとき、見直しのポイントとして注目されるのが「契約アンペア数」です。アンペア数は、同時に使用できる電気の量を左右する重要な要素であり、契約内容によって基本料金が大きく変わります。
本記事では、アンペア・ボルト・ワットの違いを整理しながら、契約アンペア数の確認方法や適正な選び方、変更方法などを詳しく解説します。ライフスタイルに合わせて、無理なく快適に過ごすための契約の見直しにぜひ役立ててください。
アンペアとは?ボルト・ワットとの違い

電気に関する基本的な単位には「アンペア」「ボルト」「ワット」の3つがあります。これらは電気の仕組みを理解するうえで欠かせない基礎知識です。
電気代を抑えるためにも、それぞれの意味を正しく理解しておきましょう。
アンペア
アンペア(A)は、電気が流れる量を示す単位です。一度に使用する電気量でもあり、家庭内で同時に使える電気の上限を決める重要な指標になります。
自宅で使用する電気のアンペア数は、電気会社との契約で決まります。電子レンジとドライヤーを同時に使うとブレーカーが落ちる場合は、契約しているアンペア数を電気の使用量が超えた状態です。アンペア数が大きくなれば使用できる電気の容量も増えますが、その分電気の基本料金も上がります。
日常生活において、アンペアは単なる数値ではなく、ライフスタイルに合った電気の使い方を考える基準といえます。効率的な電力利用と必要以上の出費を防ぐためにも、自分に合ったアンペア数を把握しておくことが大切です。
ボルト
ボルト(V)は、電気を押し出す力の大きさ(電圧)を示します。ボルト数が高いほど、電気の圧力が強くなるため、同じアンペアでもより多くのエネルギーを伝えられる点が特徴です。
家庭で使用される電圧は100Vが一般的で、大型家電製品を使う工場や店舗などでは200Vに設定されているケースもあります。家電製品によって対応する電圧が異なるため、接続する電圧が適していなかった場合は、機器の性能が発揮されなかったり、故障の原因になったりする可能性があるため注意が必要です。
ボルトは、電気代に直結しないものの、安全かつ効率よく電気を使ううえでは正しい理解と管理が欠かせません。家電の仕様や住宅設備に応じた電圧環境を整えることが、快適な生活にもつながります。
ワット
ワット(W)は、電力の大きさを示す単位です。電気が消費するエネルギーを表しているため、ワット数が大きいほど多くの電力を使用していることがわかります。
ワット数は「アンペア×ボルト」で算出可能です。同じ製品でも使う電圧や電流で消費する電力が変わり、あわせて電気代も変動します。消費電力が増えれば、その分電気代も増すため、家電製品選びには注意が必要です。
家電製品を購入する際は、仕様に記載されているワット数を確認しましょう。消費電力を把握しておけば、効率的な節電につながるだけでなく、アンペア契約の見直しを検討する際にも役立ちます。
契約アンペア数の確認方法
電気料金を見直したいときは、まず現在の契約アンペア数を確認することが大切です。契約アンペア数は基本料金に影響するため、実際の生活に合っているかどうかを知ることが節約の第一歩となります。
ここでは、契約アンペア数の確認方法を2つ解説します。
分電盤を確認する
契約しているアンペア数は、自宅の分電盤を見ると簡単に確認できます。分電盤とは、家中の電気を各部屋や回路に分けて供給するための装置です。主に玄関や洗面所付近の目につきやすい壁に設置されているケースが多く、ブレーカーが落ちた際に見たことがある方も多いでしょう。
アンペア数は、分電盤内の「アンペアブレーカー」に記載されています。一般的には「30」「40」などの数値が記されており、「30」の場合の契約アンペア数は「30A」です。ブレーカーに記載された数値を見るだけで確認できるため、特別な知識や道具は必要ありません。
一部の電力会社では、アンペア数を色分け表示しているケースもあり、視認性に配慮されています。
一人暮らしであっても、ライフスタイルや家電の使用状況によって必要な電力量は異なります。無理なく電気を使うためにも、まずは分電盤を確認して、自分の契約アンペア数を正しく把握しましょう。
検針票を確認する
電力会社から送られてくる「検針票」でも、契約アンペア数の確認が可能です。電気の使用量だけでなく、契約内容も記載されているため、手元にある場合はチェックしてみましょう。
一般的に、電気料金の仕組みには「アンペア制」と「最低料金制」の2パターンがあります。とくに、アンペア制は消費電力が電気代に直結するため、検針表の確認しやすい位置にアンペア数が記載されています。近年は、紙の検針票だけでなく、公式サイトのマイページやアプリからも確認可能です。
検針票は、毎月発行されるものであり、最新の契約状況を知るうえでも役立ちます。分電盤の位置がわからない場合やブレーカーに表記が見当たらない場合も有効な確認方法です。毎月届く検針票を活用して、自分に合ったアンペア契約を検討しましょう。
契約アンペアと電気代の関係性
前述したように、電気代を見直す際に注目すべきポイントのひとつが「契約アンペア数」です。
電気料金は「基本料金」「電力量料金」「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」の3つで構成されています。このうち、契約アンペア数が直接関係する項目が「基本料金」です。
基本料金は、契約しているアンペア数によって段階的に設定されており、アンペア数が大きくなれば金額も上がります。たとえば、10Aの基本料金は数百円程度ですが、40Aや50Aになると1,000円を超えるケースが一般的です。
電気の使用量にかかわらず、必ず発生する固定費のため、必要以上のアンペア契約をすると毎月の電気代が割高になります。
一方で、「電力量料金」は実際に使用した電気の量(kWh)に応じて決まる従量制です。多くの電力会社では、使用量が「120kWh以下」「121〜300kWh」「301kWh以上」の3段階に区分され、それぞれ異なる料金単価が適用されます。
再エネ賦課金は、国が再生可能エネルギーの普及を目的として電気の使用量に応じて毎月徴収する費用です。
このように、契約アンペア数は基本料金に影響する数値であり、自分の生活に見合ったアンペア数を検討する必要があります。とくに一人暮らしの場合は、家電の同時使用が限られていることも多く、20A〜30A程度の契約でも問題ありません。
たとえば、電子レンジやドライヤー、エアコンなどを同時に使わなければ、30A以下でも支障がないことがほとんどです。ただし、アンペア数を下げすぎると、複数の電化製品を同時に使用したときにブレーカーが落ちてしまうリスクがあります。
生活リズムやピーク時の消費電力を見直しながら、無理のない範囲で契約容量を調整しましょう。
こちらの記事では、電気代の平均について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
自宅に最適なアンペア数を調べる方法

電気代を節約するには、ライフスタイルにマッチするアンペア数に設定することが大切です。ここでは、自宅に最適なアンペア数を調べる方法を解説します。
世帯人数から求める
契約アンペア数を見直す際は、世帯人数を基準に考えるとよいでしょう。生活のなかで同時に使う家電の量は、基本的に人数に比例するため、適切な容量を判断しやすくなります。
たとえば、一人暮らしの場合は20A〜30A、二人暮らしで30A〜40A、三人以上の家庭では40A〜50A以上が一般的な目安とされています。人数が増えるほど、冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなどを同時に使う頻度が高くなり、それに応じた契約アンペアが必要です。
ただし、これはあくまで目安であり、実際には生活スタイルや家電の使い方によって適した容量は変動します。一人暮らしでも在宅勤務が中心で電子機器を多用するケースでは、30A以上の契約が適している場合もあるでしょう。
まずは世帯人数を参考にしながら、自分のライフスタイルに合った契約アンペア数を検討することが電気代の節約につながります。
必要なアンペア数の最小値と最大値から求める
日常生活で使用している家電の状況を踏まえ、必要な容量の「下限」と「上限」を把握することも契約アンペア数を決める重要なポイントです。
最小限必要なアンペア数がわかれば、過剰な契約を避けられます。一方で、最大使用時のピークを見積もっておくと、ブレーカーが落ちるリスクを抑えやすくなるでしょう。
最小値と最大値の確認方法は以下の通りです。
使用している電化製品の消費電力を確認する
まずは、自宅で使っている電化製品の「消費電力(W)」を確認しましょう。
多くの家電には、商品本体または取扱説明書にワット数の記載があります。家電ごとのワット数を加算していくと、普段使用している電力の合計を算出可能です。
続いて、算出したワット数を踏まえて「アンペア数(A)=消費電力(W)÷電圧(V)」の計算式でアンペア数に換算します。一般的に、家庭用電源の電圧は100Vのため、合計消費電力が1,500Wの場合のアンペア数は15Aです。
ピーク時のアンペア数を計算する
朝や夜など、特定の時間帯に家電を同時に使う家庭では、ピーク時を基準にアンペア数を計算すると上限を把握しやすくなります。
ブレーカーが落ちる原因の多くは、ピーク時の容量超過によるものです。たとえば、朝に電子レンジ、ドライヤー、照明、エアコンなど、消費電力の大きい家電を同時に使用する場面では、30A前後の容量が必要になる場合があります。さらに、炊飯器やコーヒーメーカーなどが加わると、一気に使用量が跳ね上がる可能性があるため注意が必要です。
このように、電気の契約容量は少な過ぎても多過ぎても無駄が生じます。ブレーカーが落ちる不便さと基本料金の負担をバランスよく考慮しながら、無理のない範囲で、ライフスタイルに合った容量を設定することが大切です。
契約アンペア数の変更方法
契約しているアンペア数は、ライフスタイルの変化や電気使用量に応じて変更できます。現在の契約容量が実際の使用状況に見合っていないと感じる場合は、電力会社へ申請しましょう。
手続きは、契約中の電力会社に連絡し、所定の申請を行うだけで進められます。多くの場合は、電話やWeb上のフォームからの申し込みに対応しており、電力会社の窓口に出向く必要はありません。
アンペア数を上げる場合は、ブレーカーの容量変更や分電盤の工事がともないます。
なお、スマートメーターが設置されている家庭では、遠隔操作によってアンペア数の変更ができる場合があります。従来のアナログメーターと異なり、立ち合いや物理的な作業が不要になるケースもあるため、対象かどうかを確認しておくとよりスムーズです。
工事費用や所要時間は電力会社や契約内容によって異なるため、申し込み前に見積もりや条件を確認しておきましょう。
契約アンペア数の見直しは、ブレーカーが落ちるリスクを回避できるほか、過剰な基本料金の見直しにもつながります。まずは現在の使用状況を整理し、自分にとって無理のない範囲で契約容量を調整しましょう。
イデックスでんきの電気料金シミュレーションで、まずはお手軽に試算してみませんか?お手元の電気検針票で、どのくらいお得になるか簡単にチェックしてみましょう。
アンペア数を下げて電気料金を節約するコツと注意すべき点
電気料金の節約には、契約アンペア数の見直しが重要です。ただし、むやみにアンペア数を下げると、かえって不便が生じる可能性があるほか、想定外のトラブルにつながることもあります。
ここでは、契約アンペア数を下げて節約するための具体的なコツと、見直す際に気をつけたい注意点について解説します。
同時に使用する家電製品(消費電力)を減らす
契約アンペア数を下げて電気代を節約するには、家電の「同時使用」をできるだけ避けたほうが賢明です。ブレーカーが落ちる主な原因は、瞬間的な電力使用量の増加にあります。使用タイミングをずらすだけでも、必要なアンペア数の抑制が可能です。
とくに、電子レンジ、エアコン、ドライヤーなど消費電力の大きい機器は、時間帯を分けて使うように留意しましょう。また、省エネ家電の導入もあわせて検討すると、無理なくアンペア数を抑える暮らしが実現できます。
節電を意識して生活する
日常の小さな積み重ねも、電気代の節約に大きく影響します。たとえば、使っていない照明や家電の電源をこまめに切るほか、必要以上に冷暖房を使わないといった工夫をするだけでも、消費電力を抑えることが可能です。これらの行動を毎日の習慣にすることで、無理のない節電を継続できます。
また、最近の家電製品は省エネ性能に優れたモデルが多く見られます。古い製品を使っている場合は、買い替えを検討すると電力消費の効率化が期待できるでしょう。
省エネの習慣が定着すると、契約アンペア数の適正化や、ブレーカーが落ちるトラブルの軽減につながり、快適な生活を維持しながら電気代の節約が実現できます。
契約アンペア数を無理に下げない
契約アンペア数を見直す際は、無理に下げすぎないように注意しましょう。基本料金ばかりを意識して、必要に満たない容量に設定してしまうと、日常生活に支障をきたす可能性があります。
とくに、複数の家電を同時に使う場面では、想定よりも電力を消費しやすく、ブレーカーが頻繁に落ちてしまう原因になります。たとえば、朝に電子レンジとドライヤーを同時に使用するだけで容量を超えてしまうことも少なくありません。
電気代の節約は重要ですが、快適な生活を保つためにも、自分のライフスタイルに見合った契約アンペア数を確保しましょう。
契約アンペアは年に1回しか変更できない
通常、アンペア数の変更は1年に1回のみと決められています。電気契約自体が1年ごとに更新されるため、使用量が少ないからといって頻繁にアンペア数を変えられません。短期間での変更には制約がある点に注意が必要です。
たとえば、アンペア数を下げたあとに、生活スタイルが変化して多くのアンペア数が必要になったとしても、すぐには対応できない可能性が高いでしょう。急な在宅勤務や新たな家電の導入など、想定外の変化にも備えておくことが求められます。
アンペア数を変更する際は、年間の変更回数に制限がある点を踏まえて慎重に検討することが大切です。生活リズムや使用家電の傾向を把握したうえで、将来的な変化も見越して判断しましょう。
集合住宅では契約アンペア数を自由に変更できない場合がある
集合住宅に住んでいる場合は、契約アンペア数を自由に変更できないケースがあります。建物全体で電力設備が一括管理されていたり、物件ごとに支えられる最大容量が定められていたりするためです。とくに築年数の古い集合住宅では、各戸で個別にアンペア数を変更できない可能性があります。
また、契約アンペア数を変更する際は、個人の判断だけでは手続きが進められないケースが一般的であり、管理会社や大家の許可が必要です。
今後アンペア数を変更する予定がある方は、あらかじめ契約条件を確認し、管理会社へ相談しておくと安心です。万が一変更が難しい場合は、使用電力を抑えたり、家電の同時使用を避けたりするなど、日々の工夫が求められます。
イデックスでんきでは、Myページへのログインに関するご案内を行っております。ログインの際には、LINEログインをご利用いただくと簡単で便利です。詳しくは、こちらをご覧ください。
まとめ
アンペアは、電気の使用量を指す単位で、電気代に大きく影響します。節電を目指すには、自宅の契約アンペア数の見直しが大切です。普段の生活を踏まえたうえで、適したアンペア数を検討しましょう。
また、より電気代がリーズナブルな電力会社に切り替える方法もおすすめです。イデックスでんきは、解約金がかからず気軽に申し込みできるほか、地元で馴染みのあるガソリンスタンドを運営している会社であるという安心感もあります。イデックスクラブカードで支払うとさらにお得になり、ポイントが貯まる点も魅力です。
電気代がどの程度お得になるかチェックできる「電気料金シミュレーション」もあるため、ぜひご活用ください。