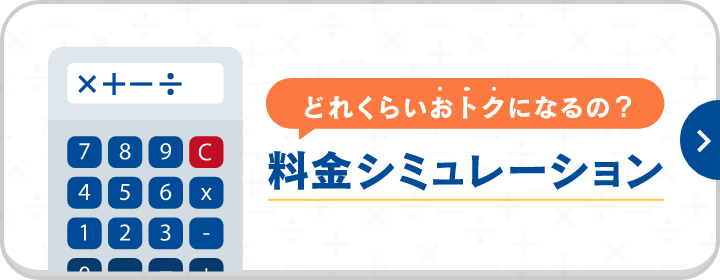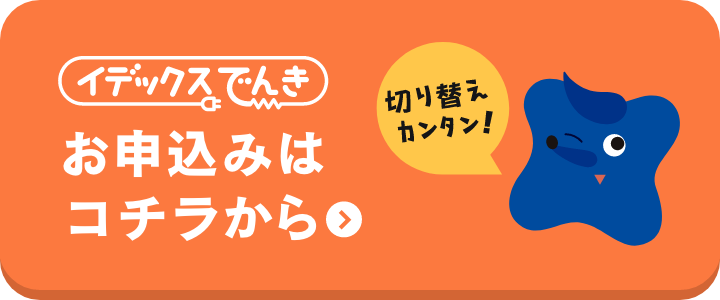消費電力の計算方法を一般家庭向けに解説!使用する単位の意味は?
2025.01.30
- 節約
- シミュレーション
- 電気
- 電気代
消費電力の計算は、家で使用している家電製品の消費電力を調べ、それをもとに行います。本記事では、計算に必要な用語や使用する単位、消費電力の計算方法について解説します。
消費電力を減らして、家計の負担を減らしたいと考えている方は多いのではないでしょうか。そのためには、まず消費電力を算出して正確に把握することが大切です。
本記事では、消費電力を計算するために理解しておくべき用語や使用する単位、計算方法について詳しく解説します。節電方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
消費電力を計算する前に

電気料金を計算するには、自宅での消費電力を知る必要があります。「消費電力」という言葉を聞いたことはあっても、その意味は知らない方も多いのではないでしょうか。
まずは「消費電力」の意味を解説します。また、計算に必要な関連用語についても詳しく解説します。
消費電力とは
消費電力とは、電気製品や機器が動作する際に使用する電力のことを指します。単位はワット(W)で、W数が大きいほど使用する電気エネルギーも多くなります。
値が大きくなると、Wの1000倍であるキロワット(kW)で表されます。1kW=1000Wと覚えておくと計算しやすくなります。
家電の消費電力は、製品に貼られたシールや取扱説明書、各メーカーの公式サイトなどで確認できます。
定格消費電力とは
定格消費電力は、家電を最大効率で使用した場合に使われる電力の最大値を示したもので、環境に配慮したい人や、電気料金を節約したい人が製品を選ぶ際に参考にしたい指標です。
定格消費電力が記載されている理由は、電子レンジやドライヤー、エアコンなど、設定温度やモードによって消費電力に大きな差が生じる製品があるためです。
また、使用する環境や使い方によって消費電力が変わるものも少なくありません。そのため、家電には最も電力を必要とする状態で動作させたときの値である定格消費電力が記載されています。
消費電力量とは
消費電力量は、電気製品を動かした時間分の電気使用量のことで、これをもとに電気料金が算出されます。
消費電力量は消費電力(W)に使用した時間を掛けて計算されるため、ワットアワー(Wh)またはキロワットアワー(kWh)で表されます。1kWhは1000Whに相当し、1kWh = 1000Whです。
年間消費電力量とは
年間消費電力量とは、家電をJIS規格で設定された条件のもとで1年間作動させた場合に、消費する電力量を表したものです。定格消費電力が家電を最大限に使用した場合の電力を示すのに対し、年間消費電力量は実際の使用環境を仮定して算出されます。
家電のなかには、充電器のようにスタンバイ状態(電源が切れているように見える状態)でも微弱な電力を消費し続けているものがあります。
また、ドライヤーや電子レンジのように使用方法によって消費する電力量が変わるものや、エアコンのように周囲の環境によって必要な電力量が変わるものもあります。
製品が実際に使われる状況を想定した値がわかると、家庭の電気代がどのくらいかかっているかの目安を算出できます。
消費電力の計算で使用する単位

計算で使用する単位は、状況によって異なりますが、一般的には以下の単位が用いられます。
● ボルト(V)
● アンペア(A)
● キロワット(kW)
● キロワットアワー(kWh)
ボルト(V)、アンペア(A)、ワット(W)は相関関係になっていて、それぞれ以下のように計算できます。
● ボルト(V)=W÷A
● アンペア(A)=W÷V
● ワット(W)=V×A
キロワット(kW)はWの1000倍を表しているため、1000W=1kWとなり、キロワットアワー(kWh)も同様に、1000Wh=1kWhとなります。
以下では、それぞれの単位の意味を解説します。
ボルト(V)
ボルト(V)は電圧を表す単位で、電圧とは電気を押し出す力(圧力)のことです。電圧を理解するには、水圧で例えるとよいでしょう。
たとえば、同じ量の水が入った2つの袋を用意し、同じ大きさの穴を開け、異なる強さで押して水を出すとします。その場合、強い力で押した袋の方が、水が出る勢いが強くなります。電気も同じように、強い圧力をかけるほど、流れる電力が大きくなります。
ただし、日本の家庭用電源の電圧は100Vのため、日本国内での使用を前提に作られた家電は、100Vの電源で動作するように設計されています。
アンペア(A)
アンペア(A)は電流を表す単位で、電流とは電源から流れる電気の量のことです。電流が大きいほど、流れる電気の量も多くなります。電流が小さいと、電気を多く必要とする製品は使用できません。
また、複数の家電を同時に使用すると、ブレーカーが落ちることがあります。これは、消費電力に対して供給できる電気の量が不足しているためです。
電力会社の料金プランの多くは、契約A(アンペア)数によって基本料金が変わります。家電の使用中にブレーカーが落ちないように、家庭内で使用するA数の合計を把握してから、契約A数を決めるようにしましょう。
キロワット(kW)
キロワット(kW)は消費電力の単位で、家電を動かすために必要な電気エネルギーのことです。製品のエネルギー効率や能力を評価する際の指標にもなります。
ワット(W)で表される場合もあります。kWはWの1000倍を表す単位で、1kW=1000Wです。
たとえば、600Wの電子レンジと800Wの電子レンジでは、800Wの電子レンジの方が早く食品を加熱できます。また、60Wの電球と100Wの電球なら、100Wの電球の方が明るくなります。
ただし、電力量が大きい製品はその分電気の使用量も増え、環境にも大きな負荷がかかります。家電を購入する際は、使用時間や頻度を考え、消費電力が多くなりすぎないものを選ぶことも大切です。
キロワットアワー(kWh)
キロワットアワー(kWh)は、時間あたりの電気の消費量(消費電力量)を表す単位で、消費電力(kW)×使用時間(h)で算出されます。
消費電力量はワットアワー(Wh)で表されることもあるので、1Whの1000倍が1kWhであることを覚えておくと便利です。
たとえば、1000Wの家電を1時間使用した場合の消費電力量は1000W×1時間=1,000Wh=1kWhとなります。消費電力が同じ製品の場合、使用時間が長くなれば電気の使用量も大きくなり、使用時間が短くなれば電気の使用量も小さくなります。
電気料金は1か月の消費電力量にもとづいて算出されるため、冷蔵庫のように常に使用する製品や、エアコンのように季節によっては長時間使用する製品は、電気の使用量が少ないものを選ぶと電気代の節約につながります。
消費電力の計算方法
一般家庭での消費電力を知るためには、家電製品の消費電力と月々の電力使用量、そして電気料金の計算方法を知ることが重要です。
それぞれの計算方法を知っていれば、電気料金を抑えられる製品や、環境への負荷が少ない製品を選べます。また、現在使用している家電製品で消費電力量が大きいものを把握できれば、買い替えを検討したり、使い方を工夫して電気料金を下げたりもできるでしょう。
それぞれの計算方法について、詳しく説明します。
家電製品の消費電力
家電製品の消費電力量を算出するには、まず製品それぞれの定格消費電力を確認します。確認した値にその製品の使用時間を掛けることで、消費電力量が計算できます。
計算式は以下のとおりです。
定格消費電力量(W)×時間(h)=消費電力量(Wh)
たとえば、定格消費電力が500Wのエアコンを1日8時間使用した場合、1日の消費電力量は500W×8時間=4,000Wh(4kWh)になります。
定格消費電力は、取り扱い説明書やメーカーの公式サイトから確認できます。定格消費電力は、家電が最大効率で稼働した場合の最大値を示すため、実際に使用される電力量は記載された値より少なくなります。
月間の電力使用量
月々の電力使用量を算出するには、家庭で使用しているすべての家電製品の消費電力量を合算する必要があります。
まずは各家電製品の消費電力と使用時間を確認し、製品ごとの電力使用量を計算します。
たとえば、定格消費電力が100Wの冷蔵庫の場合、1日あたりの消費電力量は100W×24時間=2400Wh(2.4kWh)となります。これを1か月で計算すると2.4kWh×30日=72kWhです。
ほかの製品も同じ方法で計算し、合算すれば月々の電力使用量がわかります。
ただし、冷蔵庫のように使用時間が正確に把握できる家電製品ばかりではないため、この方法だけでは月々の電力使用量を正確に算出できません。そのため、電力会社から提供される電気使用量の記録と計算結果を照らし合わせることで、月々の電気使用量をより正確に把握できます。
電気料金
電気料金は、契約容量にもとづく毎月一定の基本料金と、使用量に応じて料金が変動する従量料金の合計です。
そのため、まずは利用している電力会社の料金システムを確認し、基本料金と従量料金の単価を確認しましょう。従量料金は1kWhあたりで計算されます。
たとえば、従量料金の単価が30円だった場合、100Wの冷蔵庫を1か月使用すると、72kWh×30円=2,160円となります。
自宅で使用している家電製品の合計電力使用量から算出した従量料金に、基本料金を加えたものが、月の電気料金です。
こちらから、電気料金をシミュレーションできます。お手元に電気検針票(電気ご使用量のお知らせ)をご用意いただき、各項目をご入力ください。
消費電力を減らす方法
家庭の電気料金は、使用している家電の電力使用量の合計と、利用している電力会社の料金設定で決まります。使用している家電の消費電力量が大きいほど、電気料金も高くなり、同じ電力使用量でも、電力会社の料金設定が低ければ電気料金を抑えられます。
少しでも節電したいと考えるのであれば、以下の方法を実践してみてください。
● 未使用家電のプラグを抜く
● 省エネ家電に買い替える
● 家電製品の使い方を見直す
● スマートメーターを導入する
● 電力会社を切り替える
それぞれの方法について詳しく説明します。
未使用家電のプラグを抜く
家電製品の電源がオフになっていても、コンセントにプラグを差しているだけで微量に消費される電力のことを待機電力といいます。
待機電力は微量ですが、長期間積み重なるとかなりの電力量になるため、節電したいのであればこまめにプラグを抜きましょう。
2012年に資源エネルギー庁が実施した調査によると、1世帯あたりの消費電力量4,432kWh/年のうち、5.1%にあたる228kWh/年が待機電力でした。電気料金を1kWhあたり30円とすると、待機電力だけで年間6,840円もかかっていることになります。
そのため、使用しない家電製品はコンセントからプラグを抜くか、節電タップを利用して待機電力を防ぐことで、電気の使用量が抑えられます。
省エネ家電に買い替える
省エネ家電とは、従来の製品よりも消費電力が低く設計されているため、同じ使用時間でも電気使用量が抑えられる家電のことです。
たとえば、冷蔵庫を100Wのものから85Wのものに買い替えたとします。
100Wの冷蔵庫を1年間使用した場合、100W×24時間×365日=876kWhです。一方85Wの冷蔵庫を1年間使用した場合は、85W×24時間×365日=744.6kWhで、年間で131.4kWの消費電力量が削減できます。仮に電気料金を1kWh=30円とすると、年間で3,942円も節約できます。
とくに、10年以上前に販売された家電は、消費電力が大きいものが多いです。資源エネルギー庁の省エネポータルサイトによると、10年前と現在の家電製品を比べると、冷蔵庫で約28〜35%、エアコンで約15%の消費電力量が抑えられます。
家電を買い替えるには初期費用がかかりますが、長期的に見ると節約につながり、環境にも配慮できます。
家電製品の使い方を見直す
家電製品は使い方次第で消費電力を抑えられます。たとえば、省エネモード(ECOモード)が搭載されているものがあり、これを活用すれば消費電力を抑えることが可能です。
掃除機やドライヤーのように、強弱の使い分けができる家電の場合は、なるべく弱モードを使うようにしましょう。エアコンを使用する際は、ドアや窓の開閉を極力減らし、カーテンを使って夏は日差しを防ぎ、冬は窓から外の気温が伝わるのを抑えます。
また、室外機の周りに物を置くと冷暖房の効果が下がるため、周囲を広く保つことが大切です。さらに、室内と外気温の差が大きくなると消費電力量も増えるため、エアコンの設定温度にも注意が必要です。
ほかにも、冷蔵庫は物を詰め込みすぎないようにし、開閉回数を減らして開けている時間を短くすることで、消費電力量を抑えられます。パソコンは使用しないときは電源を切り、電源オプションを「モニタの電源をOFF」ではなく「システムスタンバイ」に変更することで節電できます。
スマートメーターを導入する
スマートメーターとは、通信機能を備えた電気のメーターで、30分ごとの電気使用量を計測し、そのデータを自動的に電力会社に送信します。
30分ごとに電気使用量が計測されるため、1日のなかでどの時間帯に消費電力が多いか、または少ないかがわかります。電気を多く使う時間帯がわかれば、その時間帯の電気料金が安くなるプランに切り替えることで、電気料金を節約できます。
現在使用しているメーターが従来型かスマートメーターかを確認するには、電力量の文字盤の表示を見ましょう。アナログ表示の場合は従来型、デジタル表示の場合はスマートメーターです。
電力会社を切り替える
2016年4月以降、電気の小売事業が全面的に自由化され、地域電力会社以外の電力会社も自由に選べるようになりました。
新電力会社の多くは、電気料金を安く提供するだけでなく、ほかの商品やサービスとセットで契約することで割引になったり、ポイントが付与されたりする独自の料金プランを提供しています。
また、再生可能エネルギーを主とした環境にやさしい電力を提供する企業も増えています。そのため、電力会社を切り替えることで、電気料金の節約だけでなく、環境への配慮も同時に行えます。
電気料金を節約したい方だけでなく、環境への負荷を減らしたい方も、電力会社の切り替えを検討してみるとよいでしょう。
こちらから、イデックスでんきの料金プランをご覧いただけます。ぜひ参考にしてください。
まとめ
一般家庭の消費電力を計算するには、家電製品の消費電力や月々の電力使用量、電気料金の計算方法を理解する必要があります。
もし、消費電力が多いと感じたら、未使用時は家電のプラグを抜き、省エネ家電への買い替えや家電製品の使い方の見直しを検討してみましょう。また、電力会社の切り替えも、電気料金を節約し、環境への負荷を軽減させる方法のひとつです。
電力会社の切り替えをされる際は、ガソリンスタンドでおなじみの新出光が提供する「イデックスでんき」をぜひご検討ください。
イデックスでんきではベーシックプラン、ミッドナイトプラン、ECOプランの3つの料金プランを用意しており、ご自身の状況に合わせてお選びいただけます。また、長期契約割引やイデックスクラブカード支払いでの割引で電気代がお得になるだけでなく、dポイントやWAON POINTも貯められます。
解約金は発生しないため、気軽にお申込みください。まずは料金シミュレーションページで、どのくらいお得になるのか試してみてください。